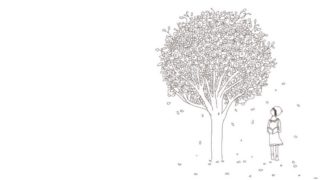信玄堤と霞堤の意味をわかりやすく解説
 霞堤
霞堤
甲斐国(現在の山梨県)の戦国武将である武田信玄の治水事業は、信玄が後世に遺した最大の功績の一つと考えられています。
その信玄の生み出した堤防として、信玄堤という名称はよく知られています。また、信玄堤に関連し、霞堤という言葉もあります。
この辺りの意味の違いが、結構分かりづらいかもしれません。
霞堤とは、武田信玄が考案したとされる特徴を持った堤防を指し、霞堤自体は各地にあります。
もともと、甲斐国では、氾濫の多い暴れ川を抱え、特に甲府盆地を流れる釜無川流域は、古来から大雨による水害が多発する地域でした。
水害のたびに、周辺の田畑や家屋に甚大な被害が生じることから、武田信玄は水害対策として、1542年から、一大治水事業に取り組み、約20年ほどの期間を要して完成させます。
信玄が行った治水システムの総称として、信玄堤という名称があります(山梨県の甲斐市にある具体的な堤防自体を指す場合もある)が、この信玄堤の堤防の特徴に、霞堤があります。
わかりやすく言えば、信玄堤という大きな防御システムの一環として霞堤という仕組みもある、あるいは、信玄堤という堤防の最大の特徴が霞堤である、と言えるかもしれません。
信玄堤は、山梨県甲斐市竜王にある堤防である。しかしその堤防だけでなく、信玄堤や聖牛、将棋頭などの治水構造物を含めた総合的な治水システム自体を信玄堤として指している場合もある。
この解説にある「聖牛」とは、堤防に打ち付ける水の勢いを弱めるために作られた、材木による三角すいのことを指します。
名前は、上部が牛の角のように見えることに由来し、この場合の「聖」とは、「スーパーやウルトラ」という意味合いだそうです。
また、「将棋頭」とは、読み方を「しょうぎがしら」と言い、石を積み上げた御勅使川の旧堤防です(参照 : 御勅使川旧堤防 将棋頭・石積出)。堤防の形状が、将棋の駒の尖った部分に似ていることに由来します。
そして、霞堤の構造に関しては、「川に不連続な切れ目を入れ、氾濫しそうなときの逃げ道を用意しておく」という仕組みになっています(参照 : 霞堤)。
強引に抑え込むというよりは、自然の力を上手に逃がしてあげる方法と言えるでしょう。
絶対に決壊しないようにする、ということを目標に、切れ目なく堤防を築いた場合、一度決壊した際に大惨事となり兼ねません。
一方、この霞堤では、決壊することを前提として、大自然を相手に「上手に負ける」ことで被害を最小限に食い止める、ということを主眼としています。
要するに、あえて水を溢れさせる仕組みにしておくことによって、大水害を防ぐ、という形態です。
(霞堤は)間が開いている、変わった堤防です。完全な遮断を敢えてしないのです。大雨で川が氾濫すると、増量した水をわざと越流させ、霞堤間に導いて、滞留させます。
そうすることで、洪水のエネルギーをパワーダウンさせるのです。
霞堤はエネルギーを喪失した洪水流を速やかに本流に戻すという機能を担っています。平地部には霞堤を2重3重に築き、氾濫したとしても、その水を釜無川に戻しやすくしたのでした。
がっちりと切れ目なく築くほうが強固な対策に見えるかも知れませんが、この場合(東日本大震災でもそうだったように)、いったん決壊してしまうと、あっという間にすさまじい氾濫と洪水が起きてしまいます。
一見、脆そうに見える霞堤のほうが、いざというときの被害が少なくてすむのです。
洪水を完ぺきに封じ込めることを目指すのではなく、洪水が起こることを前提に、流域全体の力を使って、水の流れを制御しているこのしくみは、「しなやかに強い」レジリエンスの好例ではないかと思います。
近年の水害の多発もあり、この霞堤も再び注目されているようです(「決壊しない堤防」をつくった武田信玄の発想法に学べ Forbes Japan)。
ちなみに、「信玄堤」という言葉が使われるようになったのは江戸時代の頃からで、「霞堤」と表現されるようになったのは、明治に入ってからのようです。
この霞堤という名称は、堤防が折れ重なり、霞がたなびくように見えることに由来しています。